
2019年11月1日、「渋谷から世界へ問いかける、可能性の交差点」をコンセプトに誕生したSHIBUYA QWS。
社会価値につながるプロジェクトを生み出すべく、SHIBUYA QWS Innovation協議会(以下「SQI協議会」)が
3カ月に一度主催する『QWSステージ』は、QWSでプロジェクト活動に取り組んでいる会員がそれぞれの活動の中でみつけた「新たな社会価値につながる可能性の種」のプロトタイプや活動の成果を発表する場です。
QWSステージはゲストによる問いの感性を刺激するキーノートトークから始まり、その後プロジェクトによるピッチ、表彰式という流れで進んでいきます。
今回はゲストとして東京大学大学院総合文化研究科教授 國分 功一郎 先生より、第21回目のキーノートトークとして哲学という観点から、ご自身の「問いへの向き合い方」をテーマにお話いただきました。
 また、21回目として2025年1月28日(火)に開催したQWSステージ#21では、QWSで活動する18チームが各3分間のプレゼンテーションを行いました。
また、21回目として2025年1月28日(火)に開催したQWSステージ#21では、QWSで活動する18チームが各3分間のプレゼンテーションを行いました。QWSステージ#21ではSQI協議会より、
・「SQI協議会最優秀賞」×1プロジェクト、
・「SQI協議会優秀賞」×4プロジェクト、
企業賞として味の素株式会社様より
・「味の素賞」×1プロジェクト
ADDReC株式会社様より
・「ADDReC賞」×1プロジェクト
をご用意いただきました。受賞プロジェクトは以下となります。
■SQI協議会最優秀賞
プロジェクト名:micro development(https://shibuya-qws.com/project/microdevelopment.com)
問い:渋谷とローカルで一緒に事業つくらないの?
概要:渋谷とローカルを横断した事業を作ることは今の都市/ローカルの形態にどのような影響を与えられるだろうか。ローカルでは人口減少から限界集落も多く生まれる一方で、渋谷のように多くの地域の都市化が進んでいる。今後の都市化の進む社会に対して渋谷とローカルを横断した事業を作ることは新たな仕事や働き方、暮らし方を作ることに繋がるかもしれない。双方の持続可能なまちの発展を小規模開発手法「マイクロディベロップメント」の概念からデザインする。私たちはそんな未来を想像し渋谷とローカルの事業を構想するプロジェクトです。
 ■SQI協議会優秀賞
■SQI協議会優秀賞
プロジェクト名:Kotoha(https://shibuya-qws.com/project/leuk)
問い: 消えゆく言語を守るためには?
概要:わたしたちは、みんな多様なことばを母語として生まれてきました。
私たちKotohaでは、その違いが強みとなり、すべての言語が尊重され、言語の豊かさを楽しめる人を増やすことを目指します。
 ■SQI協議会優秀賞
■SQI協議会優秀賞
プロジェクト名:comodo.(https://shibuya-qws.com/project/comodo)
問い:両親の関係が子どもに与える影響はどれだけ大きいのか?
概要:子育て支援に関する法律や制度が整備されていくなか、それらが最大限の効果を発揮するためには「子育てに対する意識」そのもののアップデートが必要ではないでしょうか。comodo.は、子育てに関して『両親の対話』を大きなテーマとして設定し、そのためにまず「パパ」へはたらきかけるイベント型サービスを提案することで、「育児に対する意識の変革」を起こし、その先に「より楽しい子育て」の実現を目指します。
 ■SQI協議会優秀賞
■SQI協議会優秀賞
プロジェクト名:親子カルタ (https://shibuya-qws.com/project/oyakokaruta)
問い:思春期の概念を崩す親子のコミュニケーションとは?
概要:『親子カルタ』は、親子間のコミュニケーション不足を解消することを目的とした革新的なゲームです。小学生以上を対象に、普通のカルタとは異なり体力制度を導入しました。
合計41枚のカードの絵札と回復カードを用いて、親子での対話を促進します。
このゲームの最大の魅力は、親と子が「協力」して楽しむことで、親の「苦労」を子供が理解し、「手伝いたい」という気持ちが育まれる点です。互いの自然なコミュニケーションが生まれることで、家庭内の雰囲気が良くなり、不登校や引きこもりへの予防策にもなります。
さらに、思春期に入る前の子供たちが積極的にお手伝いをすることで、親子間のバランスが向上し、責任感やチームワークが学べます。このプロセスが思春期の子供たちとのスムーズなコミュニケーションを育む土台となり、家庭全体の調和をもたらすことを目指しています。『親子カルタ』は、楽しみながら家事の大切さを学べる機会を提供し、親子間の絆を深めるきっかけを与えられます。
 ■SQI協議会優秀賞
■SQI協議会優秀賞
プロジェクト名:MEMORI(https://shibuya-qws.com/project/memori)
問い:自分の死は「誰に」「どうやって」伝わるのだろうか?
概要:死は、誰にも訪れるものです。そして、それがいつなのかは誰にもわかりません。
私たちが生きるこの時代は、医療技術の進歩や労働条件の向上によって平均寿命はもちろん、そのうちに占める健康寿命も延伸し続けています。特に私たちの暮らすこの国は、生活インフラが整備され、公衆衛生への意識も高く、戦争やテロによって生命を脅かされることもありません。それでも、病気や自然災害、事故によって突然の最期を迎える確率は決してゼロではありません。
ただそれは、悲観的に捉えるべき事実ではなく、何気なく過ごす毎日を有難いと感じることができる可能性を示していると考えます。
これまでの日々を振り返り、もしくはこれからの人生を思い描くことで、抱えている不安や悩みがすこしでも軽くなるなら。大切な誰かとの関係性を見つめ直すことで、明日を迎える理由が一つ増えるなら。どうしても忌避されがちな死と向き合うことで、いまをよりよく生きるためのキッカケを創出するプロジェクトです。
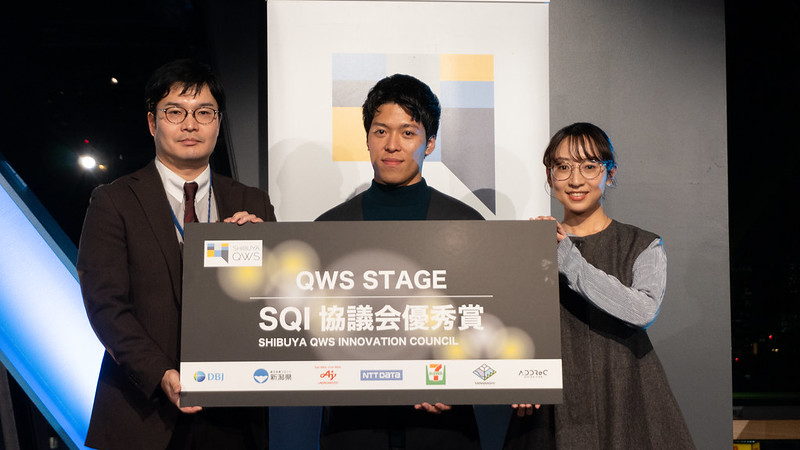 ■味の素賞
■味の素賞
プロジェクト名:Kotoha(https://shibuya-qws.com/project/leuk)
問い: 消えゆく言語を守るためには?(SQI協議会優秀賞とW受賞)
概要:上記参照
 ■ADDReC賞
■ADDReC賞
プロジェクト名:ビヘイビアプロジェクト(https://shibuya-qws.com/project/thebehaviourproject)
問い:私たちは自分たちのふるまいを、自らの意思で変えることができるのか?
概要:私たちが日常何気なく行っている「ふるまい」に焦点をあて、ふるまいの成り立ちとこれからを探る実験的プロジェクトです。日中韓の3カ国から、身体表現の専門家であるダンサーを2人ずつプロジェクトに招き、計6人のダンサーと共に東京/北京/ソウルに訪問滞在。ショッピングセンターやオフィス街など様々な場所で、都市に暮らす人たちのふるまいをフィールドワークします。そして、歴史学者・経済学者・デザイナー、社会学者など、ふるまいに関連する様々なプロフェッショナルの協力を得ながら、ふるまいの成り立ちとこれからについて分析、その活動内容を記事やドキュメンタリー番組として配信します。そして2025年2月には、ダンサー1人ひとりがこうありたいと思える新たな「ふるまい」を展示/パフォーマンスとして発表。またそうした問いかけを起点に、企業や行政などと協働しながら、社会のふるまいを自分たちの意思で再設計する活動を行います。

次回22回目のQWSステージ#22は2025年4月24日(木)を予定しております。
プロジェクトの雄姿をぜひご覧ください。
