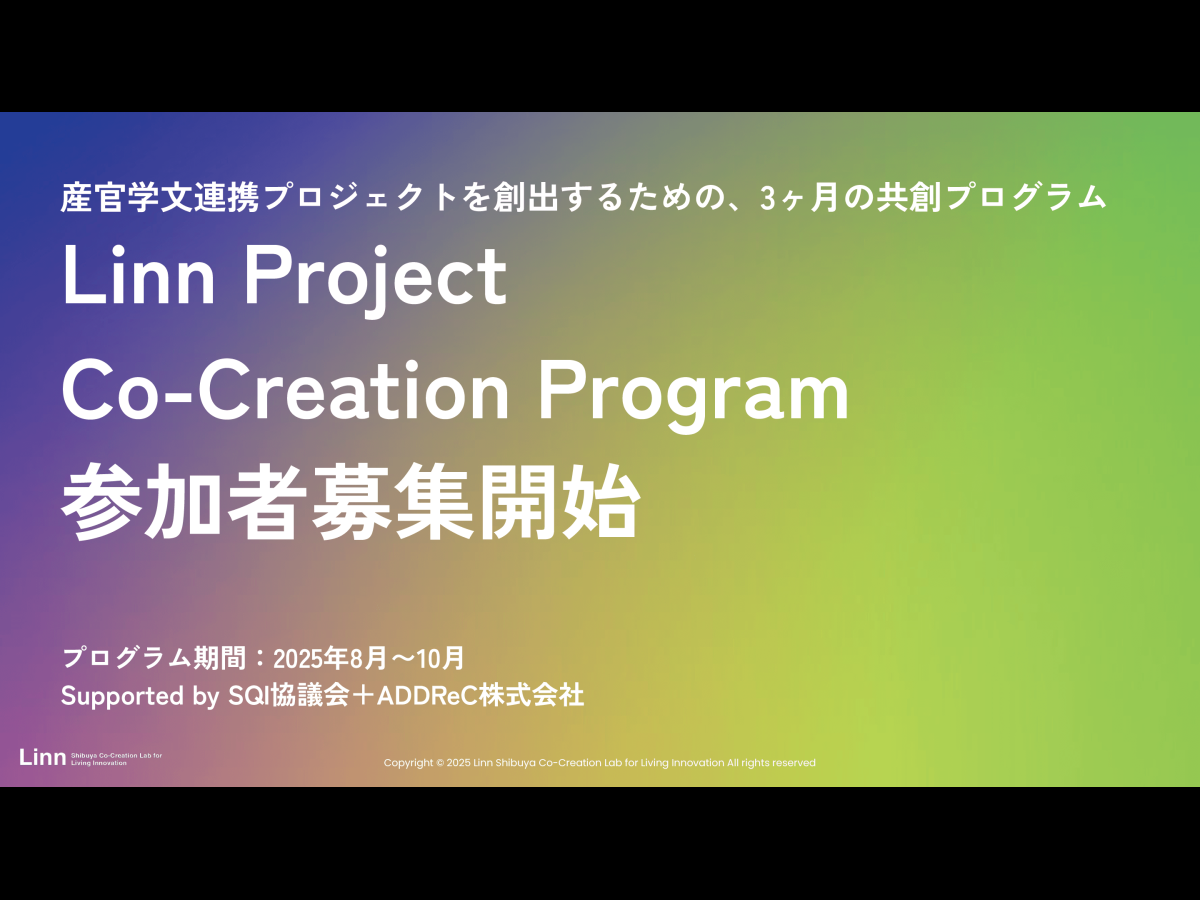
SHIBUYA QWS Innovation 協議会(以下SQI協議会)は「ワーキンググループ制度」を活用し、「暮らしと住まい」を対象にした産官学文連携プロジェクトをSHIBUYA QWSから創出する3ヶ月の共創プログラム「Linn Project Co-Creation Program」の開催を決定し、参加者の募集を開始しました。「暮らしと住まい」に関連するトピックに対して、参加者が自社/自分のリソースとの掛け合わせで、連携を前提としたプロジェクト/研究アイデアの創出を目指します。
▼プログラムステートメント
▼プログラム概要
領域の横断が難しい「産・官・学・文」が、「暮らしと住まい」というテーマを軸にして共創し大学、企業、その他の参加者の共同での研究・プロジェクト・新規事業のアイデアを創出することを目的として、3ヶ月間の「ワークショップ型のプログラム」を実施します。
・全5回/各回2.5hのワークショップ型プログラムを開催し、産官学文の参加者が共創しながら、研究・プロジェクト・新規事業のアイデアを創出します。
・各フェーズで「未来洞察」「インスピレーショントピック」「連携アイデア」を成果物として、産官学文の参加者と、共創をしながら作り上げます。
・「暮らしと住まい」にまつわる3つのサブテーマに対して、毎期で異なる3名の専門家をテーマオーナーとして招待し、“インスピレーショントピック“を提示していただきます。
第1期は以下の専門家をテーマオーナーに決定いたしました。
・第1期テーマオーナー
中山 郁英
立命館大学 経営学部 准教授
立命館大学デザイン・アート学部、デザイン・アート学研究科設置委員会 委員
合同会社ケイフー共同創業者/業務執行社員
滋賀県長浜市生まれ。大学卒業後、トヨタ自動車、コンサルティング会社、東京大学 i.schoolスタッフ等を経て、2017年より活動拠点を滋賀県長浜市に移す。合同会社kei-fu(ケイフー)プロジェクトマネージャーとして主に行政や歴史ある組織と協働。シンクタンクにて官民のフォーサイト実践にも従事。研究活動では「行政組織によるデザインの実践」をテーマに研究。著書に『行政×デザイン実践ガイド 官民連携に向けた協働のデザイン入門』(ビー・エヌ・エヌ)がある。京都工芸繊維大学大学院デザイン学専攻博士後期課程修了、博士(学術)。総務省地域力創造アドバイザー。社会教育士(島根大学)。
南澤 孝太
慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科(KMD)教授
科学技術振興機構ムーンショット型研究開発事業・目標1プロジェクトマネージャー
2005年東京大学工学部計数工学科卒業、2010年同大学院情報理工学系研究科博士課程修了、博士(情報理工学)。KMD Embodied Media Projectを主宰し、身体的経験を共有・創造・拡張する身体性メディアの研究開発と社会実装、Haptic Design Project を通じた触覚デザインの普及展開を推進。日本学術会議若手アカデミー幹事、テレイグジスタンス株式会社技術顧問
安東 慶人
日産自動車株式会社 経営戦略本部 コーポレートビジネス開発部
シニアマネージャー
アンビシャスタイムプロジェクトリーダー
家電、通信、IoT、自動車の、幅広い業界において前例のない0→1商品/サービス/事業企画創出と実現に特化したプロジェクトリーダー。アイデア、ビジネス、技術実現性、パートナー交渉すべてを同時に検討するスタイル。おもちゃから自動車、医療機器まで700以上の企画創出、400億円以上のビジネスを構築。徳島大学電気電子工学科を卒業後、総合家電メーカーで4年、ソフトバンクで11年、日産自動車で7年と22年以上チャレンジを継続。4年間シリコンバレー駐在員として、世界中のスタートアップと共創。副業として国内外のスタートアップ立ち上げを3社行った。日産自動車では自動運転、SDV時代を見据えたチャージング+、トラベルトリガー、in car game、アンビシャスタイムを0から立ち上げ、市場実装に向けて強力に推進中。
・プログラムファシリテーター
横田 幸信
i.school エグゼクティブ・フェロー
早稲田大学ビジネススクール非常勤講師
ADDReC イノベーション・ディレクター
イノベーション創出と新規事業開発の専門家。
社会の持続的成長に向けた、企業の事業創出・組織構築・人材育成までを一貫して支援してきた。2006年、九州大学大学院修士課程を修了後、野村総合研究所にて経営コンサルタントとしてキャリアをスタート。2011年にイノベーション・コンサルティングファーム i.lab を創業、代表取締役としての会社経営に加え、大手企業を中心に100件以上の新規事業・組織変革プロジェクトにコンサルタントとして携わる。主に新規事業創出、ビジネスデザイン、未来洞察、ブランド戦略などに強みを持つ。教育・研究の分野では、イノベーション人材育成プログラム東京大学i.school にてディレクターを10年間務めたほか、早稲田大学ビジネススクールにてイノベーション・マネジメント関連科目を担当。学術・産業両面からの実践知を活かし、次世代イノベーション人材の育成にも力を注いできた。著書「INNOVATION PATH ―イノベーションパス― 成果を出すイノベーション・プロジェクトの進め方」(日経BP、2016年)は、日本・中国・台湾で刊行された。発明者として合計60件(国内45件、国際15件)の特許出願・登録実績あり。発明は主に水処理技術、皮膚・生体計測技術、音声制御技術、物流技術など多岐にわたる。
・プログラムで生まれた、連携プロジェクトの共同研究・プロジェクト・新規事業は、「テーマオーナー」と「Linn事務局」が継続・推進判断を行います。
・SQI協議会とイノベーションデザインに明るいADDReC株式会社が連携し、事務局機能を担い、連携プロジェクト創出や実現にコミット、サポートをします。
▼プログラムの詳細について
プログラムの募集概要資料は以下よりダウンロードください。
・Google slide
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRTeXzIZIcT5hZl4RJUoG726i5gtbYxBtXkv0_SZ8OY34_ITl9zx37EMRfkePOgohWDSZztRBLnmif0/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
・PDF
https://drive.google.com/file/d/1oaYlR_7vNfT3evfXWLC6qBDBVmP_fwLg/view?usp=sharing
▼募集対象
以下のいずれか、または複数に該当する方・組織を募集しています。
-
・「暮らしと住まい」に関心を持ち、社会に新たな提案を生み出したい、企業/自治体関係者/大学研究者/スタートアップ/大学生
・QWSコミュニティを活用し、分野横断のプロジェクト創出に取り組みたい方
・形式的な参加ではなく将来的な共同研究・共創事業を主体的に推進する意思・能力のある方
・組織の枠や専門性を越えて、未来社会に対する構想をもとに連携を志向する方
・法人・団体等で、実務者複数名での参加が可能な組織
▼参加要件
-
・5回の全ワークショップ(下記日程)への参加ができること(参加後、希望者には2ヶ月間の任意の実行支援フェーズがあります)
・一組織からの参加は固定された最大3名まで(全日程参加必須)参加可能です。
▼参加費用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▼ 採択に関する備考(選考ポリシー)
本プログラムでは、参加者構成における多様性と公平性の確保を重視しています。以下の観点に基づいて、事務局にて参加者の選考・調整を行います。
・民間企業に偏ることを防ぐため、「企業/自治体/大学/個人・その他」などの参加枠数を想定し、バランスの取れた多様な構成を目指します。
・実際の応募状況に応じて柔軟に調整します。
◎ 選考基準
選考では以下の観点を総合的に評価します:
・多様性への寄与(組織種別、業種、世代、性別、専門性など)
・プロジェクト創出や共同研究への主体性・意欲
・組織内外のネットワークやリソースの提供姿勢
・QWSコミュニティや共創の文化への適応性
◎ 応募について
応募締め切り:7月25日(金)23:59
応募方法:以下のグーグルフォームにご回答の上、ご提出ください。
https://forms.gle/YEUegYb4FBAG4t2R9
◎ ご応募にあたってのお願い
定員を超える応募があった場合、選考の結果としてご参加を見送らせていただく場合があります。これは、応募者個人・組織の能力や熱意の有無だけでなく、プログラム全体としての多様性・構成バランスを考慮した判断によるものです。
あらかじめご了承くださいませ。
◎ FAQ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▼その他ご質問や取材について
Linn Project Co-Creation Program 事務局
東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア内 QWS
morihara@addrec.jp
